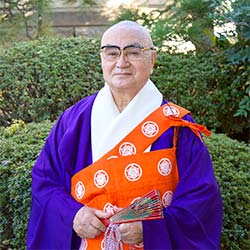
いのちと申すは一切の財(宝)の 中の第一の財(宝)なり(事理供養御書)
建治二年(1276)、身延の日蓮大聖人のもとへ「白米一俵、いもひとたわら、のりひとかご」が、使いの人を以って届けられます。当時、身延の御草庵には多い時で六十人、少ない時でも四十人在山されたと「兵衛(ひょうえ)志(さかん)殿(どの)御返事(ごへんじ)」でお述べになっておられる事でも拝察出来ます通り、衣食住は全体が苦しかった事、特に食料は毎日欠かせないもの、大変なご苦労でありました。
そうした所への白米一俵は大変なご供養でありました。大聖人のお喜びが伝わって参ります。そのお喜びを内に秘めてのお礼状が今月ご紹介の「事理供養御書」、別名「白米一俵御書」であります。
この中で大聖人は冒頭にご供養へのお礼を述べられ、続いて私達人間にとって衣食住が宝である事、それは宝の中の宝である人の生命を繋ぐものであると伝えられ、人の生命こそが一切の宝の中で第一の宝である事をお述べになられます。
今月ご紹介の聖語「いのちと申す物は一切の財の中の第一の財なり。遍満三千界無有直身命ととかれて、三千大千世界にみてて候。財もいのちは変えぬ事に候なり。」はまさにこの事であります。
このように申し上げますと、「そんな事百も承知」の返事が返ってきます。ですが、もう一度考え直して頂きたいのです。「命が大切」なのは「百も承知」でありますが、それは自分の命の事で、他人の命がどうなるかは眼中にない――。というのが実情ではないでしょうか。今、世界中で何万人というひとびとが餓死寸前の生涯を余儀なくされております。加えてウクライナを始めとする戦争の犠牲者の数が日を追う事に増加しております。
更に加えて世界全体を覆っているおそろしい空気。
ある識者が全国紙一面で「世界で民主主義が崩壊しつつあり、独裁専制主義・独裁者の台頭、それに追従する民衆が出始めている。」と警告を発しておりましたが、これはまさしく人の命の軽視、それ以外の何物でもありません。かくゆう私も八十八歳、終戦が小学二年生。戦争の恐ろしさを知らず〝神国日本〟に子供ながら手を振った一人で、その結果はみじめでした。そして八十年後の今日、又々何やらその足音が聞こえてきます。
宗祖日蓮大聖人は「いのちは財の中の財」とのご教示を根本にして「立正安国」を世界に呼びかけられました。この事を法華経の詩人・宮澤賢治は「世界中の人々の平安なくして個人の幸せはない」と表現し、人々に心の平安を呼びかけられました事、改め重く受け止め、人々・社会に呼びかけていくべき時と拝します。