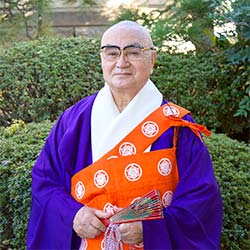
一向に法華経を行ずるが真の行者にては候なり(下山御消息)
建治三年(1277)六月、甲斐国下山郷(しもやまごう)の地頭・下山兵五郎殿にお与えになられた御文の一節が今月のご紹介の聖語であります。
本文に入る前に下山殿について少々ご紹介しますと、日蓮聖人の弟子因幡房(いなばぼう)日永上人は、下山殿の門下又は子息と伝えられ、日永上人は家の宗旨上お念仏を唱えてきました。近くの身延山に日蓮聖人が在住している事を知りますが、立場上は真正面から聴聞できないので、そっとそのお姿を拝し、読経・説法を拝聴。日蓮聖人の弟子となって日永と名乗り、自宅で法華経を拝読。この事が下山殿に知れ咎められたことから、日永上人に代わってしたためられたのが本書であり、この事があってから下山殿も日蓮聖人の信者となられるのであります。
その内容は大変な長文であり、佛教の初めから説かれ、お釈迦さまのお説きになられた法華経のこと、日本に伝来して法華経の真意が理解されておらず、私日蓮がお経文に説かれる所に随って法を弘め、そのために大難四ヶ度、小難数知れずの難に遭ってきたが、それは皆法華経弘通の条件であり、私日蓮への迫害は法華経教説上の上行菩薩の行為そのものにあたっている。更に加えて法華経こそが末法万年の人々を救済するみ教えなのだ、とお説きになられます。
この日永上人に代わって御文によって下山殿も大の日蓮聖人信徒の一人となられます。
さてここで今月ご紹介の聖語でありますが、まず本文に於いて日蓮聖人は
「お釈迦さま御一代のご説法は八万四千の法門と伝えられており、膨大な数のみ教えが説かれている。しかし、その大半は目の前で苦しんでいる人を救うために説かれた『隨他意(ずいたい)の説法、相手の立場に対しての説法』なのに対し、法華経はお釈迦さまが御自らこの事だけは末法万年の人々を救うためにお説きになられた『隨自意(ずいじい)の説法をし、御自らのご意志でお説きになられた法』である事。わけても末法万年の人々のために説かれているので、末法の時代の今は法華経こそが衆生救済、真実のみ教えである事。それが法華経の真実、南無妙法蓮華経なのである。」
とお説きになられます。下山殿でなくとも納得するご教示であります。この事を踏まえて今月の聖語
「一向に(ひたすらに)法華経を行ずるのが真の佛道修行者であり、法華経の行者である。」
とお説きになられます。
日蓮聖人は御自ら「法華経の行者日蓮」と名乗っておられます。下山殿ならずとも「自分も法華経の行者」に、と念ぜずにはおられません。私達『一向に法華経を行じ、法華経の行者』となるべき精進を重ねて参りたく存じます。